夏になるとニュースでよく耳にする「熱中症」。
でも実は、その多くが「隠れ脱水」と呼ばれる状態から始まっています。汗をかかなくても、のどが渇いていなくても、体の中で水分とミネラルがじわじわ減っている
――それが隠れ脱水。
この記事では、熱中症のメカニズムと“隠れ脱水”の正体、そして毎日できる予防策を管理栄養士の視点でやさしく解説します。
隠れ脱水とは?なぜ気付きにくいのか
「隠れ脱水」とは、自覚症状がほとんどないまま、体の中の水分やミネラル(電解質)が不足している状態のことです。
のどが渇いたり大量に汗をかく前に、体内ではじわじわと水分不足が進行しています。
特に高齢者や子ども、エアコン下で長時間過ごす方、忙しいビジネスパーソンは、のどの渇きを感じにくく、自分でも気付かないうちに脱水が進んでいることが少なくありません。
また、汗が目立たなくても、呼吸や皮膚から「不感蒸泄(ふかんじょうせつ)」と呼ばれる目に見えない水分蒸発が1日約900mlも起こっています。エアコンの効いた室内は空気が乾燥し、気付かないうちに体内の水分がどんどん失われていきます。
隠れ脱水の主なサイン
- 尿の色が濃い、量が少ない
- 口や舌が乾きやすい
- 皮膚がカサつく
- なんとなく体がだるい、頭が重い
- 立ちくらみや足のつり
参考(エビデンス)
日本救急医学会や日本老年医学会のガイドラインでも「高齢者ではのどの渇きを感じにくいため、知らない間に脱水が進行する『隠れ脱水』に注意が必要」とされています(日本救急医学会2023)。
また、体重の2%(体重60kgなら約1.2L)の水分が失われるだけで、軽度脱水状態となります。
熱中症のメカニズム ― 体内で起きていること
熱中症とは、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもることで起こる体調不良の総称です。
● 体温調節のしくみ
人は、汗をかいたり血管を広げたりすることで体温を下げています。
しかし、気温や湿度が高いと、汗が蒸発しにくくなり、体の熱がうまく外に逃げません。その結果、体温が上がり続け、熱中症を引き起こします。
● 隠れ脱水とは?
「隠れ脱水」は、体の水分や電解質(ナトリウム、カリウムなど)が、知らないうちに不足している状態です。
のどの渇きを感じにくい高齢者や、忙しくて水分補給を忘れがちな人によく見られます。
専門ポイント:
- 体重の約2%の水分が失われるだけで、脱水の初期症状(めまい・頭痛・だるさ)が出現すると報告されています(厚生労働省・日本救急医学会2023年)。
- 水分だけでなく、汗でミネラルも失われることで、体温調節機能がさらに低下しやすくなります。
管理栄養士がすすめる「隠れ脱水」予防のポイント
- こまめな水分補給を心がける
- 1日1.5~2Lを目安に、30分~1時間おきに少量ずつ。
- 朝起きたとき、入浴前後、運動前後など“決まったタイミング”で飲むのもおすすめ。 - ミネラル補給も忘れずに
- 汗をかいたときは、スポーツドリンク・経口補水液・みそ汁・梅干し・フルーツなどでナトリウムやカリウムも一緒に補給。
- 「水だけ」より、ミネラルが含まれる飲み物や食べ物を意識しましょう。 - のどの渇きを感じにくい人こそ意識を
- 高齢者、子ども、忙しい方は特に、のどが渇く前に「習慣化」するのがポイントです。
- 尿の色が濃い、朝起きたときに口が乾いている場合は、脱水傾向のサイン。 - 暑い日の外出・運動は要注意
- 炎天下や高湿度の中での活動時は、20~30分ごとに意識して水分補給を。
そのほかにも
- アルコールやカフェインは利尿作用があるため、水分補給のメインには的さないです。普段からプラス1杯の水を心がけると◎
- 汗をたくさんかく日は、バナナやキウイなどカリウムを含むフルーツも熱中症対策に効果的。
まとめ
熱中症は、体の中の「隠れ脱水」が大きな引き金になります。
のどが渇いていなくても、決まったタイミングでこまめに水分・ミネラルを補うことが、熱中症を予防するいちばんの近道です。
今日から“自分の体のサイン”に気づきながら、元気に夏を乗り切りましょう!


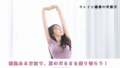
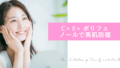
コメント